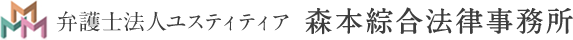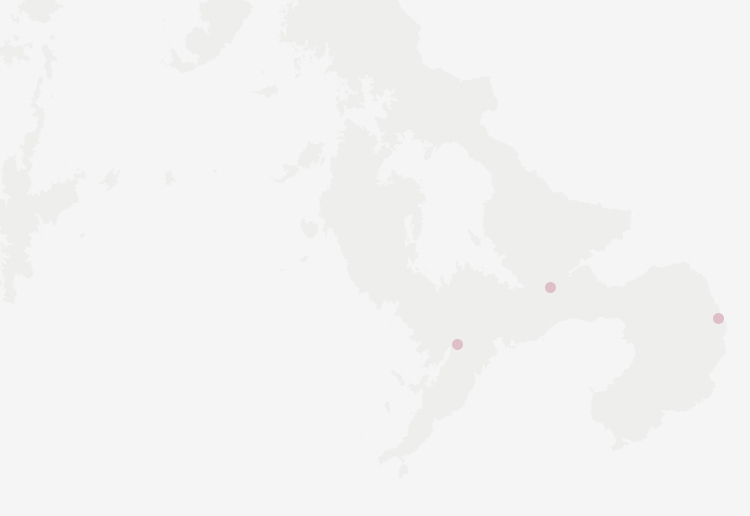1 会社法429条
取締役・執行役、監査役、会計参与、会計監査人(以下「役員等」という。)は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があり、それにより、第三者に損害を与えたときは、その第三者に対して損害賠償義務を負う(会社法429条)とされています。
また、役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合に、他の役員等もその損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯して責任を負う(430条)とも規定されています。
2 法的性質
本来取締役等は会社に対して委任・準委任の関係にあり、第三者に対しては直接法律関係にありません。取締役等の善管注意義務又忠実義務(取締役のみ)は会社に対して負担するものです。取締役等が会社における職務執行につき任務を懈怠し、その結果第三者に損害を与えたとしても、その責任は会社が業務執行機関の行為として負うべきであり、第三者に対しては、原則として、民法の不法行為(民法第709条)の要件をみたさないかぎり責任を負いません。
しかし、それでは会社に資力がない場合に、第三者である債権者は不測の損害を被るので、第三者保護のため、法によって特別に政策的配慮から認められた特別法定責任であると考えるのが通説的見解です。
そして、悪意又は重過失は、会社に対する任務懈怠につき存すれば足り、不法行為の客観的要件である第三者に対する権利侵害又は違法性は不要とされています。
これに対し、取締役は会社の雑多の事務を迅速に処理しなければならないので過失によって第三者に損害を与える機会が多く、一般不法行為によって取締役に責任を負わせると酷になるので、取締役の責任を軽減するために設けた不法行為特則説という考え方があります。
この考え方によれば、悪意・重過失は第三者に対する加害について存することを要します。
この点、最高裁大法廷昭和44年11月26日判決・民集23巻11号2150頁は、
旧商法266条の3の責任について、「もともと、会社と取締役とは委任の関係に立ち、取締役は、会社に対して受任者として善良な管理者の注意義務を負い(旧商法254条3項、民法644条)、また、忠実義務を負う(旧商法254条の2)ものとされているのであるから、取締役は、自己の任務を遂行するに当たり、会社との関係で右義務を遵守しなければならないことはいうまでもないことであるが、第三者との間ではかような関係にあるのではなく、取締役は、右義務に違反して第三者に損害を被らせたとしても、当然に損害賠償の義務を負うものではない。
しかし、法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。」とした上で、「したがって、以上のことは、取締役がその職務を行なうにつき故意または過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によって、その損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、その任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意または過失のあることを主張し立証するまでもなく、商法266条の3の規定により、取締役に対し損害の賠償を求めることができる」としました。
3 間接損害を含むか
責任の範囲について、会社が損害を受けたか否かを問わず、取締役の行為によって第三者が直接個人的に被った損害(直接損害)に限られるか、第一次的に会社に損害が生じ、その結果第二次的に第三者が損害を受けた場合(間接損害)も含むかについては、債権者保護の規定の趣旨から両方を含むものと考えられています。
4 「第三者」の範囲
「第三者」は会社以外の者をいうので、株主も含まれますが、間接損害の場合は、代表訴訟等で会社の損害を回復できる場合は、法はそちらを期待しているとの見解(神田秀樹「会社法〔第7版〕」212頁)があります。
株主が会社財産の減少による株式の価値低下という間接損害について、取締役に対して直接損害賠償請求を行うことができるかという問題は、「第三者」に株主が含まれるかという論点において議論されており、上記の見解同様に、①会社が損害を回復すれば株主も持分価値を回復する、②仮に取締役が株主に賠償しても会社に対する責任が残るなら、取締役は二重の責任を負う結果となる、③仮に、株主に賠償することにより会社に対する責任もその分だけ減少するなら、責任の免除に総株主の同意が必要なことと矛盾し、取締役に対する損害賠償債権という会社財産を株主が割取する結果となり、資本充実原則に反する、として、直接の請求を認めず、間接損害について株主は「第三者」に含まれないとする考え方が有力に主張されています。
東京高裁平成17年1月18日判決・金商1209号10頁は、
株式会社の株主は、会社の業績悪化による株価の下落について、直接取締役に対し、損害賠償請求することができるかについて、このような場合、会社が損害を回復すれば株主の損害も回復するという関係にあること、仮に株主代表訴訟のほかに個々の株主に対する直接の損害賠償請求ができるとすると、取締役は、会社および株主に対し、二重の責任を負うことになりかねず、これを避けるため、取締役が株主に対し直接その損害を賠償することにより会社に対する責任が免責されるとすると、取締役が会社に対して負う法令違反等の責任を免れるためには総株主の同意を要すると定めている商法266条5項(現行会社法423条)と矛盾し、資本維持の原則にも反するうえ、会社債権者に劣後すべき株主が債権者に先んじて会社財産を取得する結果を招くことになるほか、株主相互間でも不平等を生ずることになることから、株式会社の取締役の株主に対する責任については、商法266条が会社に対する責任として定め、その責任を実現させる方法として商法267条が株主の代表訴訟等を規定したものと解すべきであり、その結果として、株主は、特段の事情のない限り、商法266条ノ3や民法709条により取締役に対し直接損害賠償請求することは認められないとしたうえで、本件事案において特段の事由は認められず、本訴請求は許されないものであるとし、前記見解のとおりの考え方を支持しましました。
しかし、誰か(取締役を含む)の行為により会社・株主の双方が損害を被った場合に会社に独占的に請求権が帰属すべき範囲は、さほど単純に確定できるわけではなく、たとえば上場会社等については上記の見解のようにいえるとしても、取締役と支配株主とが一体である閉鎖型のタイプの会社の場合、少数株主への加害の救済を代表訴訟に限ると、加害が繰り返され実効的な救済にならない例が多いから、株主の被る間接損害につきこの損害賠償請求を認める余地はあると解すべきである(江頭憲治郎「株主会社法〔第三版〕」466頁)とされています。
最高裁第三小法廷平成9年9月9日判決・判時1618号138頁は、取締役が適法な株主総会特別決議を経ずに特に有利な払込金額で第三者割当の方法により募集株式の発行等をしたことによる株主の損害につき,
定款上株式の譲渡については取締役会の承認を要する旨の制限の付されている会社において株式の譲渡等がされた場合には、会社に対する関係でその効力の生じない限り、従前の株主が会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社はこの者を株主として取り扱う義務を負うという理論を前提に,
「株主総会開催に当たり株主に招集の通知を行うことが必要とされるのは、会社の最高の意思決定機関である株主総会における公正な意思形成を保障するとの目的に出るものであるから、同上告人に対する右通知の欠如は、すべての株主に対する関係において取締役である被上告人らの職務上の義務違反を構成するものというべきである。
本件株主総会の招集に先立って、前訴において上告人の株主としての地位の確認請求を棄却すべきものとする控訴審判決が言い渡されていたが、右判決は、その確定を待って、初めて実体法上の権利義務関係についての効力を生ずるのであって、確定に至るまでは、会社の負う前記義務に消長を来すことはない。また、仮に当時本件新株発行を早期に行う必要性が存在したとしても、株主に対する株主総会の招集の通知が会社の意思決定に関して有する意義が前記のとおりであることに照らし、取締役における事務処理上の便宜のいかんによって、右通知を行う義務が免除されることはあり得ない。してみると、これらの事情は、被上告人らに職務上の義務違反がありこれにつき悪意又は重大な過失もあったとすることを妨げるものではないというべきである。」
と判示しています。
5 民法の不法行為責任との関係
特別法定責任という考え方からすると、役員等の責任は法定責任であり、民法の不法行為責任とはその要件・効果が異なるから、役員等がその職務を行うについて故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、429条に基づく責任を負うほか、不法行為に関する民法の一般原則に基づいて損害賠償責任を負うことを認めることになります。前掲の最高裁判決も不法行為責任との競合を認めています(最高裁大法廷昭和44年11月26日判決)。
また,賠償すべき損害額を算定するにあたり,第三者に過失がある時は,過失相殺をなし得るとされています(最高裁第一小法廷昭和59年10月4日判決・判時1143号143頁)。不法行為責任という考え方からは当然のことですが,特別法廷責任という考え方からも過失相殺(民法722条2項)の類推適用を認めています。
6 消滅時効
最高裁第三小法廷昭和49年12月17日判決・民集28巻10号2059頁は、民法167条1項により10年と判示しました。
特別法定責任という考え方からは、10年の一般民事時効と解されますが、不法行為責任という考え方をとると、不法行為の3年の時効規定の適用が親和性を持つことになります。
7 損害金の利率・履行遅滞の時期
最高裁第一小法廷平成元年9月21日判決・集民157号635頁、判時1334号223頁は、遅延損害金の利率に民事法定利率の年5パーセントが適用されること、遅延損害賠償債務が履行の請求を受けたときに遅滞に陥ることを判示しました。
8 任務懈怠の例
(1) 会社が倒産に瀕した時期に取締役が返済見込みのない金銭借り入れをした場合
手形振出当時,会社の資産,営業状態から見て満期に支払いの見込みのない手形を振り出した場合(前掲最高裁昭和41年4月15日判決)
経営状態がきわめて悪化した会社が商品を購入してその決済手段として4ヶ月サイトの手形を振り出したが、その後会社は倒産して支払い不能となった場合(大阪高裁平成26年12月19日判決・判時2250号80頁、金商1484号2頁-判例解説)
(2) 会社の放漫経営
代表取締役の放漫経営のため、会社の資産状態を悪化させること(前掲最高裁昭和41年4月15日判決)。
ただし,これを任務懈怠の理由にすることには次のような批判があります。
債務超過またはそれに近い状態の株式会社は,株主が有限責任の結果失うものがないためイチかバチかの投機に走りやすいこと,および,営業を継続すれば取締役への報酬等の支払等により会社の財務状況はますます悪化することなどから,会社債権者の損害拡大を阻止するため取締役には再建可能性・倒産処理等を検討すべき義務が善管注意義務として課されており,その任務懈怠が問題となるというべきである(江頭憲治郎「株式会社法〔第3版〕」466頁)。
(3) 会社財産を横領,着服すること
(大判大正15年1月20日民集5巻115頁)
(4) 使用人・平取締役に対する監督・監視
代表取締役は,使用人,ほかの取締役の補助を得て,業務執行にあたっている場合には,不当な職務執行を阻止し、未然に防止する策を講ずるなど会社の利益を図る職責があるとされています。
9 責任を負う取締役
(1) 名目的取締役の監視義務
最高裁第三小法廷昭和48年5月22日判決・民集27巻5号655頁は,
「株主総会の取締役会は会社の業務執行につき監査する地位にあるから,取締役会を構成する取締役は,会社に対し,取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず,代表取締役の業務執行一般につき,これを監視し,必要があれば,取締役会を自ら招集し,あるいは招集することを求め,取締役会を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有するものと解すべきである。」
として,平取締役でも取締役会を通じて代表取締役の業務執行監視義務があるとしました。
最高裁第三小法廷昭和55年3月18日判決・判時971号101頁は,
取締役会を通じての業務執行監視義務について,「会社の内部事情ないし経緯によっていわゆる社外重役として名目的に就任した取締役についても同様であると解するのが相当である。」としました。
しかし,最近の下級審の裁判例は,報酬も一切受けない名目的取締役には重過失による任務懈怠があるとはいえないとの理由等で責任を否定するものが多いという傾向にあります。
旧商法下においては,株式会社においては取締役の人数が3名以上であることを要求していたため(旧商法255条),名目的取締役が発生していましたが,会社法では,株式会社において取締役会の設置が義務付けられておらず,取締役の人数は1名でもよいことになったので(326条1項,348条2項),そこをあえて取締役会設置会社にして3名以上の取締役を選任することとし(331条4項),その取締役の1名として就任した者は,名目的であっても再び厳しい責任が認められる可能性が指摘されています(前掲江頭株式会社法468頁参照)。
(2) 不実な登記簿上の取締役
最高裁第一小法廷昭和47年6月15日判決・民集26巻5号984頁は,概ね下記のとおり判断しました。
取締役への就任が、会社の創立総会または株主総会の決議に基づくものではなく、まつたく名目上のものにすぎなかつた場合においては、会社の取締役として登記されていても、本来は、会社法429条1項(当時は商法266条の3)にいう取締役には当たりません。同条項にいう取締役とは、創立総会または株主総会において選任された取締役をいうのであつて、そのような取締役でなければ、取締役としての権利を有し、義務を負うことがないからです。
会社法908条2項(当時は商法14条)は、「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事実が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定するところ、その不実の登記事項が株式会社の取締役への就任であり、かつ、その就任の登記につき取締役とされた本人が承諾を与えたのであれば、同人もまた不実の登記の出現に加功したものというべく、したがつて、同人に対する関係においても、善意の第三者を保護する必要があるから、同条の規定を類推適用して、取締役として就任の登記をされた当該本人も、同人に故意または過失があるかぎり、当該登記事項の不実なことをもつて善意の第三者に対抗することができないものと解するべきです。
最高裁第一小法廷昭和62年4月16日判決・判時1248号127頁は,辞任登記未了の旧取締役の第三者に対する責任について,
①辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合を除いては、会社法429条1項(当時は商法266条の3第1項)の責任を負わないこと,
②登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がある場合には、
会社法908条2項(当時は商法14条)の類推適用により、善意の第三者に対し、当該株式会社の取締役でないことをもつて対抗することができない結果、会社法429条1項(当時は商法266の3第1項前段)にいう取締役として所定の責任を免れることはできないと判断し,責任を限定する方向に至っています。
(3) 事実上の取締役
事実上の取締役とは,取締役の就任登記はないものの会社の主宰者として積極的に業務執行を行っていた者のことです。
「事実上の取締役たる立場を是認するためには,その者が実際上,取締役と呼ばれることがあるのみでは足りず,会社の業務の運営,執行について、取締役に匹敵する権限を有し,これに準ずる活動をしていることを必要とすると解するべき」(東京地裁昭和55年11月26日判決・判時1011号113頁、東京地裁平成5年3月29日判決・判タ870号252頁は,この要件を満たさないとして,事実上の取締役の第三者責任を否定した事例)です。
京都地裁平成4年2月5日・判時1436号115頁、金商916号45頁は,子会社を支配していた親会社の代表取締役が事実上の取締役に当たるとして商法266条の3第1項の責任を認めました。
この判決に対しては,継続的な業務執行が認められず、事実上の取締役の要件を満たしていないとの批判や親会社(またはその取締役)として子会社の業務に介入しなかったことが子会社債権者に対する責任を基礎付けるものとする点は,法人格否認の法理との均衡から見ても相当に疑問(前掲江頭株式会社法469頁)との批判がなされています。