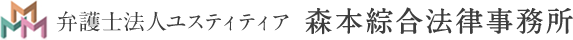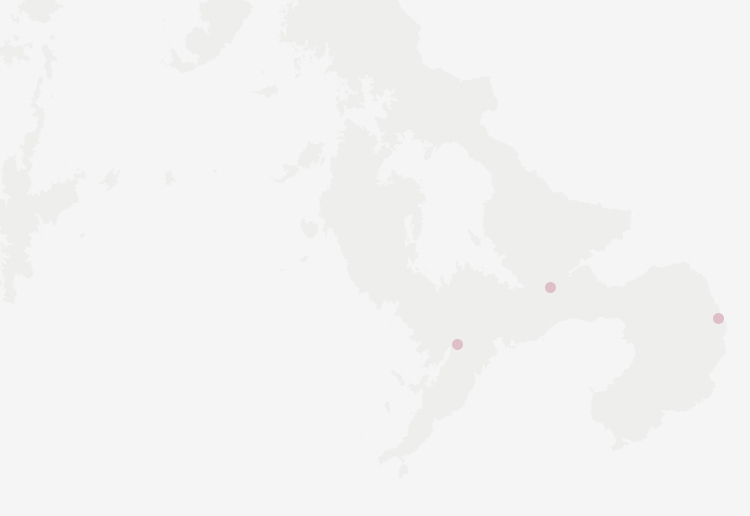遺留分制度の趣旨
被相続人は本来自己の財産を自由に処分できるのが原則です。しかし、これを全く自由に許すと、被相続人の財産に依存して生活していた相続人は困ってしまいます。相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要があることから、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられた制度です。
遺留分権者
遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人、民法1044条・887条2項・887条3項・901条)、③直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分は認められません(民法1028条)。
遺留分の割合
遺留分の割合は次のようになります。
1. 直系尊属のみが相続人の場合 被相続人の財産の1/3(民法1028条1号)。
2. それ以外の場合 被相続人の財産の1/2(同条2号)。
各相続人の遺留分(各相続人ががもつ遺留分の割合)
| 各相続人の遺留分=全体の遺留分×法定相続分 |
※ 単独相続の場合には、全体の遺留分がそのまま単独相続人の遺留分となります。
遺留分の放棄
遺留分を放棄した者には遺留分は帰属しません。相続の開始前における遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条1項)。共同相続における遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさないとされています(同条2項)。
|
家庭裁判所の事前放棄の判断基準は、
① 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
② 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
③ 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど)
などを考慮して、遺留分の放棄が相当かどうかを判断しているようです。
|
相続開始後の遺留分の放棄は自由ですので、家庭裁判所の許可は必要ではありません。
遺留分の算定
算定の基礎となる財産は①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定することとされています(民法1029条1項)。
|
遺留分算定の基礎となる財産の額
=相続人の死亡時の財産+生前贈与の価額-債務の価額
(遺贈財産を含みます)
|
① 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めることとされています(民法1029条2項)。
② 算入すべき贈与
原則として相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入します(民法1030条1項)。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を算入します(同条2項)。
相続人に対してなされた贈与で特別受益に該当するものは、相続開始の1年以上前の贈与もすべて加算されます(最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)。
具体的な遺留分の額については、遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条で定められた遺留分の割合を乗じ、遺留分権利者が複数であるときは遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、さらに、遺留分権利者が特別受益財産を得ているときにはその価額を控除して算定することとされています(最判平成8年11月26日民集50巻10号2747頁)。
|
各相続人の遺留分額 =遺留分算定の基礎となる財産の額×各相続人の遺留分-特別受益額 |
遺留分減殺請求権
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して、遺贈及び民法1030条に規定する贈与の減殺を請求することができます(民法1031条)。これを 遺留分減殺請求 といいます。
遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができ、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。
減殺請求の方法
遺留分減殺請求の方式に特に決まりはなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません(最判昭和41年7月14日民集20巻6号1183頁)。一般的には、後日裁判での証拠として提出することを考えて、配達証明付きの内容証明郵便 によって行っています。
書き方が分からない場合は、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所までご相談下さい。
減殺請求の効果
この意思表示が相手方に届いた時点で、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われ、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります(判例は、意思表示で効果の生じる形成権と考えています)。
遺留分減殺請求権の行使は、物権的に相続人に戻るという物権的効力を生じるとするのが判例の立場です(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁、最判平成11年6月24日民集53巻5号918頁)。
価額による弁償
遺留分減殺請求権が行使されると、受贈者などは現物を返還しなければならないのが原則ですが、減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物の返還義務を免れることができます(民法1041条1項)。
遺留分の請求を受けた相手方から、裁判上の抗弁として主張されるものであり、遺留分権利者の方から価額弁償を請求することはできません。
減殺の順序
① 遺贈と贈与がある場合
遺贈、贈与の順に減殺します(民法1033条)。
死因贈与のある場合は、遺贈(相続させる遺言を含む)、死因贈与、贈与の順に減殺します。
② 数個の遺贈がある場合
目的の価額の割合に応じて減殺します(民法1034条本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意思にしたがいます(同条但し書き)。
③ 数個の贈与がある場合
贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対して減殺します(1035条)。
減殺請求権の時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1042条前段)。相続開始の時より10年を経過したときも同様です(同条後段)。
民法1042条前段の「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与・遺贈があったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいいます(大判明治38年4月26日民録11輯611頁)。また、民法1042条は遺留分減殺請求権そのものを対象とする規定であり、遺留分減殺請求権が行使された結果として生じた目的物返還請求権は民法1042条の消滅時効にはかかりません(最判昭和57年3月4日民集36巻3号241頁)。
遺留分減殺請求について、争いがある場合にも、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所へご相談下さい。