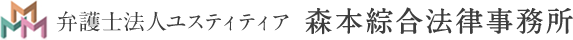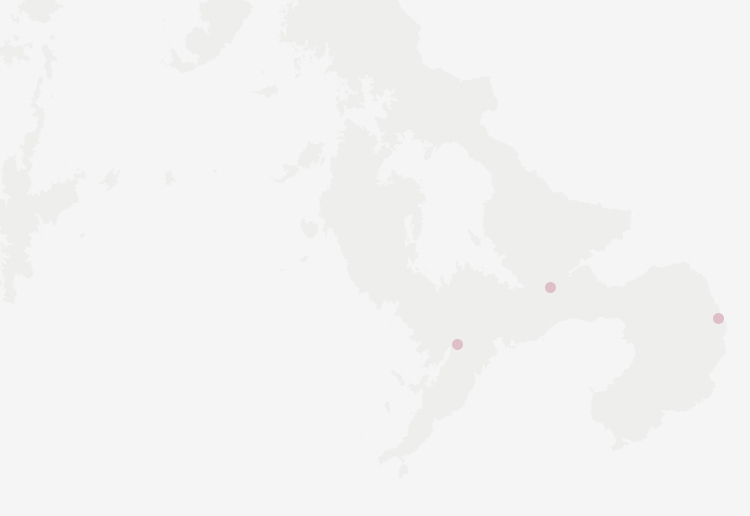ボトルキープ論とは
利息制限法所定の制限利率に引き直してもなお貸金残元本が存在している時点で,ある支払期日において借主が支払をしなかったとしても,従前の超過支払い額を累積すると,上記支払期日に支払うべき金額を支払っていたことになるから,借主は期限の利益を喪失しないとの主張のことをいいます。
超過支払額をあたかもボトルキープのようにストックし,将来の支払期日における支払に充当することからこのようにいわれています。
具体例
例えば,平成13年1月20日に300万円借入れ,60回分割で,毎月20日支払,1ヶ月分として,元金5万円,約定利息3万円を返済(元利均等分割返済方式)となっている約定は,利息制限法に従って,利息は15%分(例えば1万円)を返済という約定に縮減されます。
・平成13年2月20日 8万円返済
・同年3月20日 8万円返済
・同年4月20日 8万円返済
・同年5月20日 8万円返済
ここまで約定通り支払ったところで平成13年6月20日に全く支払をできず,同月25日に8万円返済したが,期限の利益を喪失したとします。
しかし,実際は,8万円(元金5万+利息3万)も払う必要がなく,6万円(元金5万+利息1万)で足りるはずです。
よって,1ヶ月あたり2万円ずつ払いすぎていることになります。
・平成13年2月20日 6万円返済でOK 2万円余分に払いすぎ
・同年3月20日 6万円返済でOK 前月と合計4万円余分に払いすぎ
・同年4月20日 6万円返済でOK 前月までと合計8万円余分に払いすぎ
・同年5月20日 6万円返済でOK 前月までと合計10万円余分に払いすぎ
・同年6月20日 約定通りの8万円を払う義務がないことは当然で,ただ,6万円の返済をすれば足りるはずです。既に10万円余分に払いすぎているので,利息制限法に従えば既に支払い済みであると考え,期限の利益は喪失することはないと考える考え方です。
当事務所が勝ち取った裁判例
利息制限法1条1項所定の利率を超える利息の契約をした場合,債務者は,同条項所定の利率を超える利息の支払いをする義務を負うことはないから,当該金銭消費貸借契約において,各弁済期に約定の分割返済金及び利息の支払いを怠った場合は期限の利益を喪失する旨の合意がされていても,債務者が分割返済金と同条項所定の利率による利息を支払えば,期限の利益を喪失することはないものと解される。
シティズの主張する第1回貸付の期限の利益喪失が平成13年9月10日第2回貸付の期限の利益喪失が平成15年8月11日であるとの主張に対し,平成13年9月10日までに支払った金額は15%の利息を支払うものとして計算した金額の総額を超えている。平成15年8月11日までに支払った金額は15%の利息を支払うものとして計算した金額を超えていると判断し,したがって,期限の利益の合意に係る元金又は利息の支払いを遅滞したときにはあたらないとしました(長崎地裁平成18年8月29日判決・兵庫県弁護士会HP。後に上告取下にて確定。判決はこちら→https://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060829n.pdf)。
この理論の問題点
① この理論の欠点は,当初早い段階で遅滞が生じた場合には救済できないことです。その場合には他の理論を持ち出さざるを得ません。
② これに対し,ボトルキープ論を否定した判決は,制限超過利息の支払いは無効であり,元利金と指定して支払ってもその指定は無意味であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに当然に充当されるものというべきである(最高裁昭和39年11月18日判決・民集18巻9号1868頁参照)としていました(長崎地裁平成19年4月24日判決・判例集未搭載・福岡高裁の差戻審)。
しかし,元本充当は,債務者の利益のためであるのに,これを債務者の不利益のために使うのは背理であるとの批判は可能です。
裁判例
松山地裁西条支部平成19年3月9日判決(対信用信販)・兵庫県弁護士会HPもボトルキープ論を採用しています。
最高裁判所の考え
最高裁第一小法廷平成26年7月24日判決・判時2241号63頁
最高裁第三小法廷平成26年7月29日判決・判時2241号63頁
はいずれも,このような考え方をとることなく,昭和39年の最高裁との整合性のみを議論して,貸金業者に有利な判断をしています。
すなわち,元利均等分割返済方式(指定された回数に応じて元本及び利息の合計支払額が毎月同額となるよう分割して返済する方式)によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係について,
「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはない。」
と判断しました。