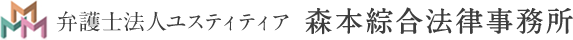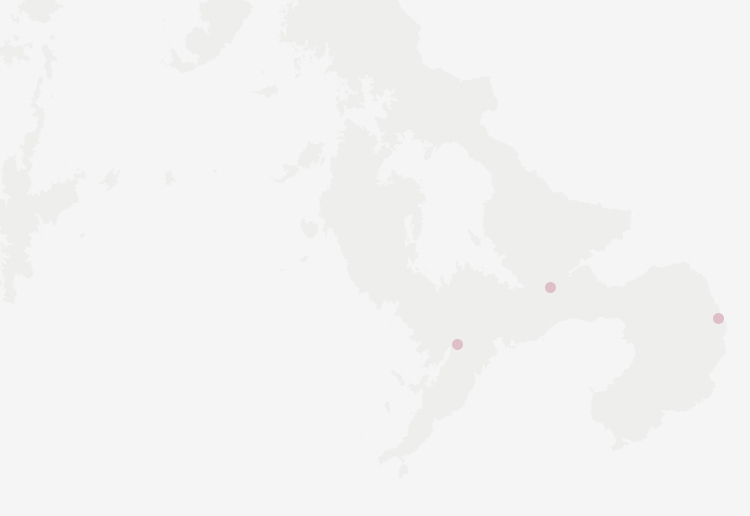取締役の会社に対する責任
1 別個に規定を設けた趣旨
取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人(以下「役員等」といいます)は,会社に対して委任または準委任の関係に立ち(330条),善良なる管理者の注意義務を負っており(民法644条),取締役は,法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し会社のために忠実にその職務を行う義務(忠実義務)を負います(355条)。したがって,善管注意義務違反,忠実義務違反があったときは,債務不履行責任を負います(民法415条)。
それにもかかわらず,会社法が役員等の会社に対する責任の規定を設けたのは,一般原則としては不十分であると考えたからです。特殊の債務不履行的性質を有する損害賠償責任であるといえます(東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟(Ⅰ)〔第3版〕」206頁参照)。
2 旧商法266条の規定
(1) 旧商法266条1項1号
取締役が利益配当の制限規定に違反して,利益配当議案を総会に提出したとき,または,中間配当の制限規定に違反して金銭の分配をしたときは,違法配当または分配額について会社に対し連帯して弁済する責めを負う旨規定していました(旧商法266条1項1号)。
違法配当の責任で,資本充実の要請から,違法配当の結果財産の減少を防止し,会社債権者を保護するために特に規定されたもので無過失責任であると解されていました。これに対し,会計監査を職務とする監査役,また大会社では会計監査人の監査を前提にし,特に大会社の複雑な経理について,取締役に無過失責任を課すことは酷であるとして,過失責任と解し,無過失の立証を取締役に課すことによって免責させるべきであるとする見解も有力に主張されていました。
現行の462条1項,2項は,旧商法266条1項1号を過失責任にする等して引き継いだ規定です。
(2) 旧商法266条1項2号
取締役が財産上の利益供与禁止規定に違反して,株主の権利行使に関して財産上の利益を供与したときは,会社は利益の供与を受けた者に対しその利益の返還請求権を有していますが,取締役も供与した利益の額に付会社に対し弁済する責任を負うとされていました。
現行の120条4項は,旧商法266条1項2号を一部過失責任にして引き継いだ規定です。
(3) 旧商法266条1項3号
他の取締役に対し金銭の貸し付けをなしたときは,貸付をなした取締役は,会社に対し連帯して未だ弁済のない額について賠償する責めを負うとされていました。自己取引のうち最も危険性を内在し,自己取引と別に規定し,貸付について取締役会の承認の有無を問わず,弁済期に弁済がなければ,弁済する責任を規定したものであるから,無過失責任と解する見解が通説とされていました。
現行の会社法では,このような規定は削除されました。
(4) 旧商法266条1項4号
取締役会の承認を得てした自己取引でも,対価の不当,債務不履行などによって会社が損害を被ったときに,取締役は連帯して賠償責任を負うとされていました。
この規定についても無過失責任とする見解が通説とされる一方,取締役会決議を経ている限り自己取引は適法行為であること,取締役会決議を経た場合に無過失責任を負い,取締役会決議を経ない場合に旧商法266条1項5号の過失責任を負うというのは不均衡であるから,無過失を立証できれば責任を免れるという見解も有力に主張されていました。
取締役の承認を受けた自己取引については,発行済株式総数の3分の2以上の多数をもって免除できることになっていました(旧商法266条6項)。
現行の423条3項は,旧商法266条1項4号を過失責任化したしたもので,428条1項の場合(自己のために利益相反取引の直接取引をした場合)は,無過失責任なので,旧商法266条1項4号を引き継いだ規定ということになります。現行の会社法では,旧商法266条6項の規定は削除されました。
(5) 旧商法266条1項5号
法令定款違反に基づく損害賠償責任ですが,任務懈怠に基づく損害賠償責任として会社法423条1項に引き継がれました。
3 任務懈怠責任
役員等は,その任務を怠ったときは,会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負います(423条1項)。
取締役の任務には,法令を遵守して職務を遂行することが含まれます(355条)。法令は,会社法上の具体的な法令だけでなく,公益保護を目的とする全ての法令です。例えば,外国語会話教室を経営する株式会社が破産した場合について,特定継続的役務提供取引を行う事業者として,特定商取引法を遵守する義務があり,法令遵守体制を構築し,必要な指示を行うべき義務を負っていたとして取締役の責任を認めた大阪高裁平成26年2月27日判決・判時2243号82頁等があります。
取締役は,善良なる管理者の注意義務に違反する業務執行行為により会社に生じた損害を賠償する責任も負います。この判断は,「行為当時の状況に照らし合理的な情報収集・調査・検討等が行われたか,および,その状況と取締役に要求される能力水準に照らし不合理な判断がなされなかったかを水準になされるべきであり,事後的・結果論的な評価がなされてはならない。」(江頭憲治郎「株式会社法」第3版・433頁)とされています。
また,「取締役が業務執行の際どの程度の情報収集・調査等を行え
ばよいかが問題であるが,弁護士・技師その他の専門家の知見を信頼した場合には,当該専門家の能力を超えると疑われるような事情があった場合を除き,善管注意義務違反とならない。」(同書433頁注(2))とされ,会社法の世界でも顧問弁護士制度が重要であることが指摘されているといってよいと思います。
4 経営判断の原則
業務執行行為の判断の誤りの関係でしばしば問題となるのが経営判断の原則です。
(1) 経営判断の原則とは何か
経営判断の原則とは,取締役が会社及び彼自身の権限内において,ある決定を下した場合に,その決定に合理的な根拠があり,かつ彼が最良の利益であると誠実に信じた事柄以外には影響を受けずに,彼自身の裁量と判断の結果として,当該決定を下したのであれば,裁判所は,取締役の経営事項については干渉しないし,裁判所の判断を以て,取締役の判断に代替せしめることはないという考え方をいいます(有斐閣「新版注釈会社法(6)」276頁)。
(2)経営判断の原則は,取締役の合理的な裁量権である
取締役は,会社と委任または準委任の関係にあります。会社との契約の目的は,民法の委任関係同様一定の事務を処理するための統一的労務となっています。つまり,受任者である取締役は,自己の知識・経験・手腕によって適当に処理する自主性を与えられています。よって,取締役には,経営に関する一定の裁量権が与えられていると考えられます。
このように,取締役には一定の裁量が与えられていると考える以上,受任者である取締役が裁量を逸脱するような経営判断をするか,委任者と受任者との間に存する信任関係に背くような任務懈怠を含むものではない限り責任を問われるべきではありません。
取締役が行う判断は,緊急を要する判断もあり,また複雑な経済情勢をみながら何が会社にとって適切かということを常に判断していかなければならないものです。したがって,取締役の裁量権は極力広範に与えられ,その時々の事情に合わせて機動的な判断ができるというべきです(以上,片岡大輔「取締役の経営判断に伴う法的責任」立命館法政論集第1号収容245頁~249頁参照)。
(3)経営判断の原則の判断基準
取締役の会社に対する経営判断の責任の有無に関する判定基準として,これまでの下級審裁判例では,①経営判断の前提となった事実の認識への過失の有無,②その事実認識に基づく意思決定の推論過程・内容に関する合理性の有無の2点を採用しているとされています(東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟(Ⅰ)〔第2版〕」242頁参照)。
(4)アメリカの判例法との関係
この考え方は,アメリカの判例法理及びそれを取り込んだ制定法における経営判断の原則を参考にしたものですが,アメリカの経営判断の原則は,取締役の意思決定過程に不合理がないことを審査し,判断内容の合理性には一切踏み込まないなどの点で,我が国における実務及び学説とは異なっていると指摘されています(江頭憲治郎「株式会社法〔第3版〕」注(3)435頁)。
(5) 下級審の裁判例
この点,下級審の裁判例として,下記のようなものがあります。
① 東京地裁昭和55年9月30日判決・判時1005号161頁,判タ434号197頁
「事業の特質,判断時の状況等を考え合わせて,当初から会社に損害を生ずることが明白である場合又はそれと同視すべき重大な判断の誤りがある場合は格別,与えられた経営上の裁量権の範囲内であれば,その出所進退の点は別として,取締役としての任務を懈怠したことにはならないものと解すべき」としています。
② 福岡高裁昭和55年10月8日判決・判時1012号117頁,判タ433号149頁
「たとえ会社再建が失敗に終わりその結果融資を与えた大部分の債権を回収できなかったとしても,右取締役の行為が親会社の利益を図るために出たものであり,かつ,融資の継続か打ち切りかを決断するに当たり企業人としての合理的な選択の範囲を外れたものでない限り,これをもって直ちに忠実義務に違反するものとはいえない」としています。
③ 東京地裁平成5年9月21日判決・判時1469号25頁,判タ827号39頁
「取締役は,定款に掲げる会社の目的の範囲内で経営判断を行う裁量権を有する」とした上,「経営が著しく客観的合理性を失し,右裁量権の範囲を逸脱した場合は,それが会社の目的として定款に掲げられている行為であっても免責されない」としました。
④ 長野地裁佐久支部平成7年9月20日決定・資料版商事法務139号196頁
「企業の経営悪化について取締役の法的責任を問うことは,経営判断の裁量の問題もあって,それ自体一般にはきわめて困難である」とし,子会社に対する債務保証等の支援が親会社に損害が生じさせたとして提起された代表訴訟において株主に担保提供が命じられました。
⑤ 東京地裁平成16年3月26日判決・判時1863号128頁
「判断の前提となった事実の認識に看過し難い誤りがあり,又は判断の過程,内容が取締役として著しく不合理であるか否かを基準として判断するのが相当である。」「当該判断の前提となった情報の収集,分析が当時の状況,事柄の重要性等に照らして明らかに合理性を欠き,又は判断の基礎となった情報を元にした判断の過程,内容に著しく不合理な点があった場合には,当該取締役の判断は裁量の範囲を逸脱し,善管注意義務に違反するものとなる」と判断しました(銀行の資金融資の実行につき,責任を肯定)。
⑥ 東京地裁平成16年6月23日決定・金商1213号61頁
経営不振の状態に陥っているグループ企業を支援するために同社の優先株を引き受ける旨を決定したことについて,「三菱自動車の破綻を防ぐためには支援を緊急に行うことが必要であることが認められるし,一方で,リコール隠しに関する事実関係も三菱自動車の新経営陣の下で明らかにされつつあることを考慮すれば,三菱重工の取締役がこの段階で三菱自動車への支援を決定したことが,その時点での客観的な情勢についての分析・検討に不注意な誤りがあり合理性を欠いていたとまでは認められないし,その結果に基づいてこの時期に支援決定をしたことが明らかに不合理な判断であるとはいえない」として善管注意義務違反を否定しました。
⑦ 東京地裁平成17年3月3日判決・判時1934号121頁
「取締役の判断の適法性を判断するに当たっては,取締役の判断に許容された裁量の範囲を超えた善管注意義務違反があるか否か,すなわち,意思決定が行われた当時の状況下において,当該判断をする前提となった事実の認識の過程(情報収集とその分析・検討)に不注意な誤りがあり合理性を欠いているか否か,その事実認識に基づく判断の推論過程及び内容が明らかに不合理なものであったか否かという観点から検討がなされるべきである。」としました(整理支援金の支出につき,責任を否定)。
⑧ 東京地裁平成18年4月13日判決・判タ1226号192頁
株式公開買付期間中に株式の市場価格が買付価格を上回ることがあった場合において,「要請元の企業あるいはそのグループ等との円滑な取引関係の維持や発展の要否など複雑多様な諸要素を勘案したたうえで行われる経営判断に属する事柄であり,・・・応募後に当該株式に係る市場価格が買付価格を上回った場合には,常に応募を撤回しなければならないという一義的処理が要請されるべきものではなく,これらの点についての経営者の判断は,具体的な状況下において,前提とした事実の認識に不注意な誤りがなく,その事実に基づく行為の選択に著しく不合理な点がない限り,尊重されるべきものである。」として,公開買付への応募を撤回しなかった会社の取締役らに善管注意義務違反・忠実義務違反はないとしました。
⑨ 大阪高裁平成19年3月15日判決・判タ1239号294頁
1株あたり純資産額を上回る額での自己株式取得(非公開株)につき,「会社が非上場の自己株式を取得するに当たり,その取得価格を算定するに当たっては,当該株主から当該価格により株式を取得する必要性,取得する株式数,取得に要する費用からする会社の財務状況への影響,会社の規模,株主構成,今後の会社運営への影響,資本維持の観点から当該価格の1株あたり純資産額からの乖離の程度など諸般の事情を考慮した企業経営者としての専門的,政策的な総合判断が必要となるというべきであり,取締役には一定の裁量を認めるのが相当である。」とし,取締役の善管注意義務には違反しないとしました。
(6) 最高裁平成22年7月15日判決・判時2091号90頁
(事案の概要)
A社は,事業再編計画を計画し,B社をA社の完全子会社であるC社に合併して不動産関連業務等を含む事業を担わせることを計画,A社の経営会議(A社の代表取締役Yらが参加)において,B社をC社との合併前に完全子会社とすること,B社の株式の買取価格は払込金額である5万円が適当であること,助言を求められた弁護士もB社の株主である加盟店等との関係を良好に保つ必要性があるのであれば許容範囲である旨の意見を述べ,B社株1株当たり5万円の買取価格を決定しました。
株式の買取に応じない株主との間では株式交換の手続を予定,監査法人にB社の株式評価を算定依頼したところ,1株当たり1万円以下とされました。
A社の株主であるXは,Yらに対し取締役としての善管注意義務違反として株主代表訴訟を提起しました。
(判断の概要)
「本件取引は,B社をC社に合併して不動産賃貸管理等の事業を担わせるというA社のグループの事業再編計画の一環として,B社をA社の完全子会社とする目的で行われたものであるところ,このような事業再編計画の策定は,完全子会社とすることのメリットの評価を含め,将来予測にわたる経営上の専門的判断にゆだねられていると解される。そして,この場合における株式取得の方法や価格についても,取締役において,株式の評価額のほか,取得の必要性,参加人の財務上の負担,株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定することができ,その決定の過程,内容に著しく不合理な点がない限り,取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。」とした上で,
①B社の株主にはA社が事業の遂行上重要であると考えていた加盟店等が含まれており,買取りを円満に進めてそれらの加盟店等との友好関係を維持することが今後におけるA社及びその傘下のグループ企業各社の事業遂行のために有益であったこと,
②非上場株式であるB社の株式の評価額には相当の幅があり,事業再編の効果によるB社の企業価値の増加も期待できたこと,
③本件決定に至る過程においては,A社の役付取締役全員で構成され,A社及びその傘下のグループ企業各社の全般的な経営方針等を協議する機関である経営会議において検討され,弁護士の意見も聴取されるなどの手続が履践されていることなどを考慮し,本件価格決定において,取締役の判断として著しく不合理なものということはできず,善管注意義務に違反したということはできないとしました。
5 不作為による任務懈怠
(1)問題の所在
任務懈怠は,他の取締役・使用人に対する監督義務違反を含む取締役の不作為について問題となります。
従業員や他の取締役・執行役が行った故意・過失に基づく違法又は不適切な行為の結果,会社が損害を被った場合に,取締役・執行役が監督上,善管注意義務違反を理由とする責任を負うかどうかとの関連では,内部統制システムの整備・運用が重要な意味を有しています。
(2)内部統制システム
会社法の下では,内部統制システム等の整備の基本方針は,取締役会設置会社では取締役会の専決事項とされ(362条4項6号),大会社(資本金5億円以上,負債総額200億円以上)には,内部統制システム等の整備の基本方針の決定が義務付けられています(348条3項4号,4項)。
法務省令によれば,取締役会設置会社以外の大会社は,①取締役の執行に関わる情報の保存・管理に関する体制,②損失の危険の管理に関する規程その他の体制,③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制,④使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制,⑤会社・親会社・子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制につき,取締役の過半数をもって決定しなければならない(会社規則98条1項),また,⑥取締役が2人以上ある場合は業務の決定が適正に行われることを確保するための体制,および,⑦監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を決定に含まなければならない(会社規則98条2項,4項)。会社が業務の適性を確保するためには,ある程度以上の規模の会社にはその組織体制構築が必要であるとの考え方に基づくもので,会社法の制定時に大会社に対して義務づけられています(江頭憲治郎「株式会社法〔第3版〕」375頁注(4)参照)。
6 消滅時効
(1)問題の所在
取締役の任用契約は,商法503条の附属的商行為です。とすれば,取締役の任用契約に基づいて発生する会社の取締役に対する損害賠償責任についても,商事性が認められるのではないかが問題となります。
(2)最高裁判決
最高裁第二小法廷平成20年1月28日判決・民集62巻1号128頁
「商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが,法によってその内容が加重された特殊な責任であって,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない。また,取締役の会社に対する任務懈怠行為は外部から容易に判明し難い場合が少なくないことをも考慮すると,同号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任については商事取引における迅速決済の要請は妥当しないというべきである。」とし,消滅時効の期間については,「商法522条所定の5年ではなく,民法167条1項により10年と解するのが相当である。」と判示しました。
7 損害金の利率・履行遅滞の時期
最高裁第一小法廷平成26年1月30日判決・集民246号69頁,金商1439号32頁
最高裁は,遅延損害金の利率について,民法所定の年5分の割合としました。
「商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが,法によってその内容が加重された特殊な責任であって,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない(最高裁平成18年(受)第1074号同20年1月28日第二小法廷判決・民集62巻1号128頁参照)。そうすると,同号に基づく損害賠償債務は,商行為によって生じた債務又はこれに準ずるものと解することはできない。
したがって,商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分と解するのが相当である。」
また,履行遅滞となる時期については,
「商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,期限の定めのない債務であって,履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当である。」と判示しました。
これらの判断は,会社法423条1項の下でも同じく妥当すると考えられています(弥永真生「本件批判」ジュリスト1465号3頁)。