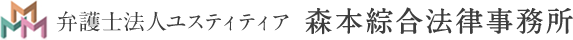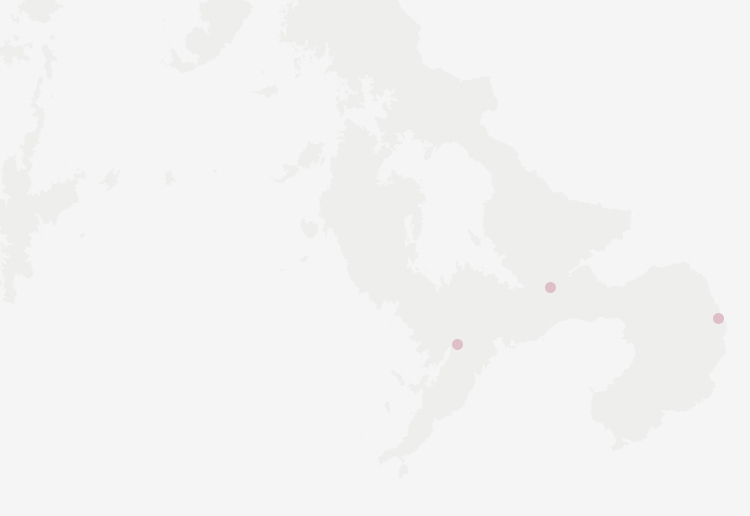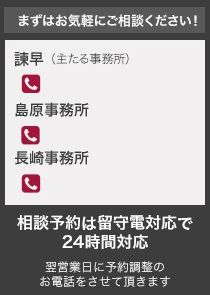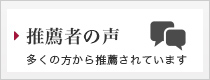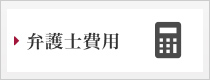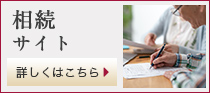裁判所は、「債務者が支払い不能にあるとき」は、申立により破産手続開始決定をすることになっており(破産法15条1項)、債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を自己破産といいます。自然人の破産の大半はこの自己破産です。
経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。
財産の一部は失ってしまいますが、免責になれば全ての借金を支払わなくてよく、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
① 弁護士に依頼した時点で、貸金業者の直接の取立て行為が禁止されます。
⇒弁護士介入後の直接取立は貸金業法に違反します(貸金業法21条1項9号)。
違反した場合は、貸金業者は行政処分の対象となるほか(登録取り消し,又は1年以内の業務の全部若しくは一部の停止-同法24条の6の4第2項)、刑事罰の対象にもなります(2年以下の懲役、300万円以下の罰金又はこれらの併科-同法47条の3)。
その他、民事上不法行為として損害賠償責任を負うことがあります。
したがって、まともな業者であれば、弁護士の通知が届いた時点で取立をすることはありません。
② 免責が確定すれば借金を支払わなくてもよくなります。
⇒法律的には、裁判をすることも強制執行をすることもできなくなりますが、任意に支払うともらった側は、返す必要がないという性質の債権に変わる(自然債務といいます)と解釈されています。
③ 破産申立以降に得る財産や収入はご自身のものになります。
デメリット
① 資格制限のある職種があります。
⇒弁護士(弁護士法7条5号)、公認会計士(公認会計士法4条4号)、生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法279条)、警備員(警備業法3条)、旅行業務取扱管理者(旅行業法11条の2)等一定の職業に就くことができません(なお、会社法は、取締役、監査役の欠格事由から破産者を除外しています〔会社法331条1号〕が、委任の終了事由としては残っています〔民法653条〕ので注意が必要です)。免責になれば、それらの職に就くことは可能です。
② 住宅ローン付き不動産を有している場合、その不動産は競売になるか処分されます。
⇒破産手続を選択すると、支払を止める結果不動産は競売になるか、あるいは破産手続の中で任意売却され、持ち家を残すことができません。
持ち家を残したいというご本人の希望がある場合、その希望が叶えられるかはご相談戴く必要があります。多重債務の中、破産をしないで住宅ローンを支払い続ける場合には、客観的に契約どおり支払っていけるかどうかの判断を慎重に行う必要があります。
③ 信用情報機関(ブラックリスト)への登録
⇒一定期間信用情報機関に登録される結果、新規の借入れ(クレジット契約の締結を含む)が困難になります。一般には5~7年程度です。
④ 免責許可を受けてから7年間は再び自己破産しても免責にはならない
⇒一度「免責許可決定」が出された場合には、それから7年間は自己破産の申立てをしても、免責許可の決定は出ません(破産法252条1項10号)。
但し、裁量免責の余地は残されています(同条2項)。
弁護士に依頼するメリット
自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。
・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは前記破産のメリット記載のとおり貸金業法で定められています。
・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成を弁護士に任せることができます。
・免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類作成や裁判所の手続の中でどのように対応すればよいのかをしっかりサポートします。
・借金を整理する手続選択について的確な指導が得られます
借金を整理していく手続は、破産に限らず色々な手段がありますが、お客様自身の希望と状況に合わせて、的確な手段をサポートしていくことが可能となります。
破産手続の種類
破産手続は、本人の財産状況により同時廃止事件もしくは、管財事件の2つに分けられます。
同時廃止事件
同時廃止事件とは、申立人の財産が少なく、換価しても破産手続費用(破産管財人の報酬等)にも足りないことが明らかな場合に、裁判所が破産手続開始と同時に破産手続を終了させる事件のことをいいます(破産法216条)。
管財事件
これに対し、管財事件とは、破産手続開始と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の破産手続開始時点の財産を換価して、これを破産債権者に公平に分配して清算手続きをする事件のことをいいます。
管財事件は財産を換価して、債権者に配当を行う配当事件と換価しても、財団債権を支払うだけで破産債権に対して配当できないときに破産手続を廃止する異時廃止事件(破産法217条)とに分けることができます。
管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。財産があることが前提で、その分手続も複雑となり、裁判所に納める予納金も50万円程度準備することが必要になります(これは弁護士の費用とは別です)。管財事件の場合、破産者にはさらに次のような制限が付きます。
① 住所の移転と旅行の制限
破産管財人が選任された場合は、債務者の財産を換価、処分し、各債権者に配当しなければならないので、破産手続が終了するまでは、裁判所の許可なくして、住所の移転、長期間の旅行はできないことになっています(破産法147条、377条2項)。
② 破産管財人によって郵便物が管理されます
破産管財人が選任された場合は、破産者宛に届いた郵便物も、破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできることになっています(破産法81条、82条)。
管財事件のうち、少額管財事件として予納金が最低20万円程度で済む類型があります。裁判所により多少取扱が異なっていますが、長崎地方裁判所で考えられているのは次のような類型です。
予納金が最低20万円程度で済む類型
(1) 自由財産拡張型
手続終了まで、申立代理人、管財人及び裁判所の間において協力をしながら、破産者の財産状態などの調査を経て、自由財産の拡張が可能であれば、事件を異時廃止で終了させる手続です。
破産の時点で現金なら99万円まで、価値の低い中古車、解約返戻金の少ない生命保険は自由財産として保有し続けられます(破産法34条1項1号、民事執行法131条3号)が、この自由財産の範囲を拡張してもらうために管財人の調査を行うものです。
(2) 個人事業者型
申立人が現在個人事業を営んでいる場合、または近い過去に個人事業を営んでいた場合です。個人事業者は、財産や取引が事業と個人生活との間で分離されていないことが多く、財産状況を解明するため管財人の調査が行われます。
(3) 法人代表者型、法人併存型
申立人が現在法人代表者である場合、または近い過去に個人事業を営んでいた場合です。法人代表者については、個人の財産と法人の財産との混同が生じやすいため、管財人の調査が行われます。
(4) 資産調査型
破産に至る経緯や資産の内容などに疑義があり、管財人の調査によって疑問点を解明しなければならないような場合です。保証債務や住宅ローンを除いた債務が多額の場合などに管財人の調査が行われます。
(5) 否認権対象行為調査型
偏頗行為や財産減少行為の存在がうかがわれ、否認権の行使が可能か否かを管財人が調査するケースです。
(6) 免責観察型
免責不許可事由に該当する行為の内容及び程度が重大で、そのままでは免責不許可となることが見込まれ、裁量免責を受けるために、管財人による免責不許可事由の内容についての調査・生活状況(主として家計収支)についての指導監督などが必要とされるケースです。
自己破産の流れ
自己破産手続き費用
1 非事業者の破産事件
債務総額1000万円以下(引き直し前の額)の場合:20万円(税抜)
債務総額1000万円以上(引き直しの額)の場合:35万円(税抜)
ただし、親族関係がある場合で、かつ同一裁判所で同時に進行する場合には、5万円を減額します。
2 事業者の破産事件
法人の自己破産事件 100万円(税抜)
事業者の自己破産事件 50万円(税抜)
いずれの場合も、予納金という裁判所に納める金額は別に用意して戴きます。
自己破産相談者の声
借金返済のために、かなり生活が苦しい状況でしたので、思い切って一度相談してみようと思いました。弁護士というと、普段接することもない方ですし、正直最初は怖いというイメージだったのですが、とても親身に話を聞いてくださいました。わかりやすい例え話をまじえながら説明してくれたので、よく理解できました。自己破産手続きのお陰で借金がなくなり、ほっとしています。